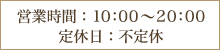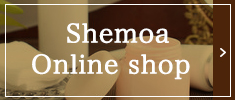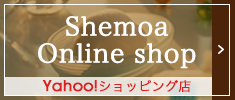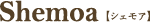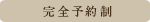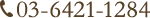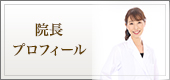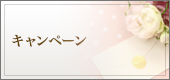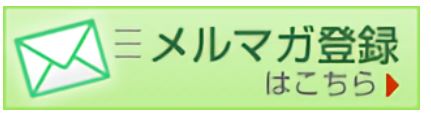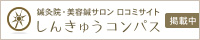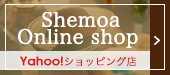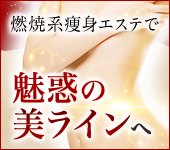夏の疲れをとる養生法
「何となく疲れが取れない」…
夏の疲れはお盆過ぎくらいからやってきます。
体の重だるさの原因は
暑さによる消耗や食欲不振、屋内の冷房による
外気との気温差や高い湿度などにより、
体にかかった負担が「疲れ」として出てきます。
秋を爽やかに迎えるためにも、夏の疲れは早めに回復しておきましょう!
東洋医学では
体内の「気」「血」「水」のバランスが
崩れることが一つの原因と考えられています。
「何となく…」を放っておくと
慢性疲労に繋がりますので、ぜひ早めのケアを心がけていきましょう
迎える秋冬に向けて身体を整える
また、夏は「心(心臓)」に負担がかかりやすく、迎える秋は、乾燥から「肺」の不調が起こりやすくなります。夏の疲れを感じている人は自分の体調を見直して、心と肺の不調にも注意をしながら身体全体を整えるよう心がけましょう。
夏の疲れを引きずっていると、秋冬になってかぜやインフルエンザにもかかりやすくなってしまいます。早めの対処でしっかり回復し、食欲の秋、スポーツの秋を元気に楽しみたいものですね♪
日本の夏の特徴は『暑』と『湿』
要するに、日本の夏はとても蒸し暑いことです。
これは、人体の働きにも大きく影響します。
- 『暑』は、体の水分を失わせます
- 水分が多く失われると、体の『気(エネルギー)』も傷ついてしまいます。 こうなってしまうと、体のだるさ等の症状が出やすくなります。
- 『湿』が重度になると、体の正常な機能を滞らせます
-
『湿』の重度化は胸苦しさや手足や体のだるさ等が生じます。
また、『湿』は胃腸に影響しやすいという特徴があり、食欲不振やお腹のはり、悪心嘔吐や下痢などが生じます。特に、胃腸がまだ整っていない小児には、『湿』の影響が出やすいので、注意が必要です。
このような夏の特徴を踏まえて、
夏の不養生や疲れが出てくるのがこの時期なのです。
過ごしやすくなっても食欲不振や倦怠感・だるさ・風邪気味などといった症状が続き、「秋バテ」と言った状態が起こります。
東洋医学からみた疲れの原因
①『夏の暑さに負けて体力を消費したもの』
夏の暑さは“心”に負担がかかります。
心は血液を巡らし熱を調節していますが、心の疲れがたまってくると外からの熱に弱くなってしまいます。
夏場に元気でも、夏の暑さで体力が落ちてきた秋口では少しひんやりとした朝晩の寒さにやられてしまうことがあります。
②『冷房や冷たい食べ物で体温調整機能が弱まってしまったもの』
真夏はクーラーをガンガンにかけて冷たいものを飲み食いしても、外の気温が高いのでなんとかバランスを保つことが出来ます。(冷えに弱い人や胃腸が弱い人は、この夏の時点で体調を崩しています。)
しかし、屋外と屋内の寒暖差で体温を調節する自律神経が乱れ、体温調整機能は弱まってしまっています。
そうすると夏が終わりに近づき、日中暑く朝晩冷えるようになると体温を調節できず、寝てる間に冷えて、だるさや腰痛・風邪を引いたりします。
③『天候の変化』も大きく関係してきます。
お盆を過ぎると夏至の頃よりも大分日照時間を短くなっています。
日を浴びる時間が短くなると精神安定や睡眠にかかわるセロトニンの分泌量も減るため、敏感な人は秋口から不調を感じてしまいます。
さらに秋は日本列島を低気圧が覆ったり台風がきたりと、気圧が変化しやすい時期なのでだるさを感じやすくなります。
このように秋口は体調を崩しやすい原因がいくつかあります。
では、対策はどうしたらいいのかというと・・・
まずは、胃腸を立て直し元気をつけることです!
秋は旬のものが多く栄養のあるものが多く出回るので、上手に食べると体力をつけることが出来ます。
栄養があるからといってそのまま多く摂ると、弱っている胃腸にさら負担をかけてしまいますので、消化のよい温かい料理にして食べるようにしましょう。
また、弱った体温調節機能は、「外気に触れる」「汗をかく」ことで高めることができます。
体温調節機能は、身体が感じる温度に対して自律神経の命令で働くので、一定の温度の室内にずっといると自律神経も活発には働かず体温調節機能は低下します。
外気と日光にあたる時間をきちんととり、自律神経の働きを高めてあげましょう。
そして、軽く体を動かしたり、湯船にしっかりと浸かったりして、汗をきちんとかくようにしてください。
いきなり激しい運動をすると怪我をする怖れがあるので注意が必要ですが、少しずつウォーキングやラジオ体操など軽い運動をしておくと体力もつき、秋バテしにくくなります。
秋は食べ物もがおいしく、気候も過ごしやすくイベントも多い時期なので、体調を崩しているのはもったいないですよね。体質や体調・既往歴などにもよりますが、秋に体調が悪いという人は夏のお盆過ぎあたりから、とくに気を付けるようにしてくださいね。

まとめ